���ǂ̂Ƃ���iDeCo��NISA�ǂ����������́H�i�O�ҁj

iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j�́A�����N��������N���Ȃǂ̌��I�N����₤���߂ɓ������ꂽ�C�Ӊ����̎��I�N�����x�ł��B����ANISA�i�j�[�T�F���z������ېŐ��x�j�́A�l�}�l�[���s��ɌĂэ��ݎs���������������ƂƂ��ɁA�l�̒����I�Ȏ��Y�`���̂��߂ɃX�^�[�g������ېŐ��x�ł��B
�X�^�[�g�����o�܂͈Ⴄ���̂́A�^�p�v��20.315%�̐ŋ��������邱�ƂȂ��A�����悭���Y�Â��肪�ł��鐧�x�Ƃ��āA���݂ǂ�������ڂ��W�߂Ă��܂��B����ł́AiDeCo��NISA�͂ǂ��炪�����̂ł��傤���H����̑O�҂ł�iDeCo��NISA���ꂼ��̐��x�̊T�v�ƃ����b�g�E�f�����b�g�ɂ��Ă��������܂��B
iDeCo��NISA�̐��x�T�v
iDeCo��NISA�͕ʁX�̐��x�̂��ߕ��p�ł��܂��B�������ANISA�ɂ́u�݂���NISA�v�Ɓu�i��ʁjNISA�v��2��ނ���A�ǂ��炩���I�Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
iDeCo(�l�^�m�苒�o�N��)�̐��x�T�v
| �Ώۋ��Z���i |
�E���{�m�ی^���i(����a���A�ϗ��ی��Ȃ�) |
|---|---|
| ���p�\���� | 60�܂� |
| ��ېŌ��x�z |
�����҂̐E�ƂƃP�[�X�ɂ�� |
| �Œ�ϗ��z | ���z5,000�~�i�N�z6���~�j�ȏ� |
| �ϗ����@ |
�E�����ςݗ���(����26���[�t) |
| ���Z���i�w�����@ |
�ϗ����w�� |
| �^�p�����̈��o�� | 60�܂ŏo���s�� |
| ��ېőΏ� |
�E�^�p�v |
| �����Ǘ��萔�� | ���Z�@�ւɂ���āA��167�~�`600�~���x�Ƃ��낢�� |
�݂���NISA�̐��x�T�v
| �Ώۋ��Z���i |
�E���������M�� |
|---|---|
| ���p�\���� | �ō�20�N�ڂ܂� |
| ��ېŌ��x�z |
�N��40���~ |
| �Œ�ϗ��z |
���Z�@�ւɂ�� |
| �ϗ����@ |
���Z�@�ւɂ�� |
| ���Z���i�w�����@ |
�ϗ����w�� |
| �^�p�����̈��o�� | ���ł��\ |
| ��ېőΏ� | �^�p�v |
| �����Ǘ��萔�� | �Ȃ� |
���NISA�̐��x�T�v
| �Ώۋ��Z���i |
�E���������M�� |
|---|---|
| ���p�\���� | �ō�5�N�ڂ܂� |
| ��ېŌ��x�z | �N��120���~ |
| �Œ�ϗ��z | ���NISA�͐ϗ����x�Ȃ� |
| �ϗ����@ | ���NISA�͐ϗ����x�Ȃ� |
| ���Z���i�w�����@ |
�ϗ����w�� |
| �^�p�����̈��o�� | ���ł��D���Ȗ������w���\ |
| ��ېőΏ� | �^�p�v |
| �����Ǘ��萔�� | �Ȃ� |
���Z�@�֑I�т͐T�d��
iDeCo��NISA�����ۂɉ^�p���n�߂�ۂɂ́AiDeCo��NISA����舵���Ă�����Z�@�ւɁAiDeCo��p�����ENISA��p�������J���K�v������܂��B�������AiDeCo������NISA�����������̋��Z�@�ւŕ����̌����������Ƃ͂ł����A�ۗL�ł���̂͂��ꂼ���������݂̂ł��B
�������AiDeCo������NISA���������Z�@�ւɎ��K�v�͂Ȃ��A�ʁX�̋��Z�@�ւ�iDeCo������NISA�������J�����Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��A���Z�@�ւɂ���Ď�舵�����Z���i��e��萔���Ȃǂ��قȂ邽�߁AiDeCo�̏ꍇ��NISA�̏ꍇ���A�������J�����Z�@�ւ͐T�d�ɑI�т܂��傤�B
NISA�Ɣ�r�����uiDeCo�v�̃����b�g
�@�@�ϗ����i�|���j���S�z�����T���ɂȂ�
iDeCo�ł͐ϗ����i�|���j���S�z�u���K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���v�ƂȂ�A��������T������܂��B���̂��߁A�ېŏ���������l�́A�����ŁE�Z���Łi�̏������j���ߐłƂȂ�܂��B�����ł͉ېł���鏊�����z�̐ŗ��ɉ����āu5%�`45%�~�|���S�z�v�̌��ŁA�Z���ł͏������̐ŗ��u10%�~�|���S�z�v�̌��łł��B
�|���̍ŏ��z�����z5,000�~�i�N�z6���~�j�ȏ�ŁA�|���̏���z�́A�����҂̐E�Ƃ�P�[�X�ɂ��ȉ��̂悤�Ɍ��܂��Ă��܂��B�|���̋��z�͔N1��ύX�\�ł��B
| �����҂̎�� | �|���̌��x�z | |
|---|---|---|
|
�������ی��̑�1����ی��ҁ� |
�N�z81.6���~ |
|
|
�������N���̑�2����ی��ҁ� |
��ЂɊ�ƔN�����Ȃ���Ј� |
�N�z27.6���~ |
| ��ƌ^�m�苒�o�N���ɉ������Ă����Ј� |
�N�z24���~ |
|
| ��ƌ^�m�苒�o�N���Ɗm�苋�t��ƔN���ɉ������Ă����Ј� |
�N�z14.4���~ |
|
| �m�苋�t��ƔN���ɉ������Ă����Ј� | ||
| �������Ȃ� | ||
|
�������N���̑�3����ی��ҁ� |
�N�z27.6���~ |
|
�i��1�j�����N������{iDeCo�A�����N���t���ی����{iDeCo�̍��Z�g
�������A�u���K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���v�K�p�̂��߂ɂ́A�����N���̑�1����ی��ҁE��3����ی��҂̏ꍇ�͊m��\�������邱�ƂɂȂ�܂��B�����N���̑�2����ی��҂̏ꍇ�́A�Ζ���ł̔N�������ł��T���̐\�����\�ł��B
�A�@�^�p���Y��莞�Ɍ��I�N�����T���E�ސE�����T��������
iDeCo�ʼn^�p�������Y�̎����@�ɂ͈ȉ��̕��@������܂��B
- �N���Ƃ��Ď��i5�N�ȏ�20�N�ȉ��j
- �ꎞ���Ƃ��Ĉꊇ�Ŏ��i70�ɂȂ�܂łɎ��j
- �ꕔ���ꎞ���ŁA�ꕔ��N���Ŏ��
�^�p���Y��N���Ƃ��Ď��ꍇ�́u���I�N�����T���v���K�p�ɂȂ�܂��B�ق��̔N�������Ƃ̍��v�z����A���I�N�����T���z�������������Ƃ��ł��܂��B���I�N�����T���z��65�Ζ����Ȃ�70���~�A65�Έȏ�Ȃ�120���~�ł��B
�^�p���Y���ꎞ���Ƃ��Ď��ꍇ�́A�ق��̑ސE�蓖�i�ސE���j�ƍ��Z���āu�ސE�����T���v���K�p�ɂȂ�܂��B�ސE�����T���z�̌v�Z�̍ۂɂ́AiDeCo�̉����Ҋ��ԁ��Α����ԂƂ݂Ȃ���܂��B
�s�ސE�����T���z�̌v�Z���@�t
| �Α��N�� | �ސE�����T���z |
|---|---|
| 20�N�ȉ� | 40���~�~�Α��N��
��80���~�����̏ꍇ��80���~ |
| 20�N�� | 800���~�{70���~�~�i�Α��N���|20�N�j |
iDeCo�ł̉^�p���Y�����I�N���̎O��60�`64��5�N�ԂɏW�����ĔN���Ŏ��A�ق��̑ސE�蓖�Əd�Ȃ�Ȃ��悤�Ɉꎞ���ł̎���x�点��Ȃǂ̍H�v�����邱�Ƃɂ���āA����ɐߐł̉\��������܂��B
NISA�Ɣ�r�����uiDeCo�v�̃f�����b�g
�@�@60�ɂȂ�܂ʼn^�p���Y�̈��o�����ł��Ȃ�
iDeCo�ł̉^�p�����́A�����Ƃ���60�ɂȂ�܂ň����o�����Ƃ��ł��܂���B�|���̋��z�͗]�T�����͈͓̔��Ō��߂܂��傤�B
�Ȃ��A60����^�p���Y�����ɂ́A�m�苒�o�N���́u�ʎZ�����ғ����ԁv�iiDeCo�Ɗ�ƌ^�m�苒�o�N���ł̉����Ҋ��ԁ{�^�p�w�}�Ҋ��ԁj��10�N�ȏ�K�v�ł��B�ʎZ�����ғ����Ԃ�10�N�����̏ꍇ�́A�ȉ��̂悤�ɔN�����Y�̎J�n�N��J�艺���ɂȂ�܂��B
�s�ʎZ�����ғ����Ԃ�10�N�����̏ꍇ�̎J�n�N��t
| �ʎZ�����ғ����� | �J�n�N�� |
|---|---|
| 8�N�ȏ�10�N���� | 61���� |
| 6�N�ȏ�8�N���� | 62���� |
| 4�N�ȏ�6�N���� | 63���� |
| 2�N�ȏ�4�N���� | 64���� |
| 1�����ȏ�2�N���� | 65���� |
�A�@�萔����������
iDeCo�́A�u�^�c�Ǘ��@�ցv�ł�����Z�@�ւ̂ق��A�u�����N������A����v��u�����ϑ�����Z�@�ցv�ɂ���ċƖ����s���Ă��邽�߂ɁA���낢��Ȏ萔����������܂��B
- �����萔���F2,777�~�i����̂݁j
- �����Ǘ��萔���F���Z�@�ւɂ���Č�167�~�`600�~���炢�i����103�~�͊|���[�t�̂ǂ�����萔���j�B�ϗ��������ɉߋ��ɐςݗ��Ă����Y�̉^�p�݂̂��s���ꍇ�͌�64�~�`500�~���炢�B�l�b�g�،���Ђ̕��������ł��B
- �^�p���Y��掞�̐U���萔���F�U���̂�432�~
���ɁA�����Ǘ��萔���͋��Z�@�ւɂ���ĈقȂ��ɁA�����ɂȂ�Ƃ��Ȃ�̋��z�ƂȂ邽�߁A�e��萔���͋��Z�@�֑I�т̃`�F�b�N�|�C���g�̈�ł��B
�B�@�ΏۂƂȂ�^�p���i�������Ă���
���Z�@�ւɂ���Ď�舵���Ă���^�p���i�⏤�i���͈قȂ��Ă��܂��B����ɁA2018�N5���̖@�����ɂ��A���Z�@�ւ���舵������Z���i�̐���35���i�܂łɐ�������邱�ƂɂȂ�܂����B2018�N9�����_��35���Ă�����Z�@�ցi��FSBI�،��A���O�،��j�ł́A�ڍs�[�u���Ԃ��I���2023�N4�����܂łɏ��i���̍i�荞�݂��s���܂��BiDeCo�̑ΏۊO�ɂȂ鏤�i�́A�u�X�C�b�`���O�v�i���i�p���ĕʂ̏��i���w�����邱�Ɓj�𔗂���\�������邽�ߋC�����܂��傤�B
iDeCo�Ɣ�r�����uNISA�v�̃����b�g
�@�@�ΏۂƂȂ�^�p���i�̃��C���i�b�v������
���Z�@�ւɂ���Ď�舵�����Z���i�ɈႢ�͂���܂����AiDeCo�ɔ�ׂ�ƁA�^�p���i�̎�ނ��͂邩�ɑ����ł��B���NISA�Ȃ犔�������M���i�ꕔ�ł������ʼn^�p���Ă��铖�M���Ȃ�OK�j�̂ق��ɂ��A�����O�̊����EETF�i�����M���j�EREIT�i���s���Y�����M���j�ȂǁA�،���Ђ��l�ڋq�ɔ̔����Ă���悤�ȋ��Z���i�͂قڑΏۂɂȂ�܂��B�������w�������ꍇ�́A�ӂ��̊���Ɠ��l�Ɋ���D�҂����܂��B
�݂���NISA�ł��A���i���ɐ���������iDeCo�ƈႢ�A���ɏ��i���ɏ���͂���܂���B�u�̔��萔���������v�u�M����V��1.5%�ȉ��v�u�������z�^�łȂ��v�Ȃǂ̏������������������M����ETF�ŁA���Z���ɓ͏o������Ă���ΑΏۏ��i�ɂȂ�܂��B2017�N9��28�����_�ŁA158�{�̓����M����3�{��ETF���ΏۂɂȂ��Ă��܂��B
�A�@�^�p���Y�͂��ł������o���ł���
NISA�͉^�p���Ă�����Z���i�p����A�K��̎�n���ȍ~�͂��ł��o���ł��܂��B
�B�@�萔��������
NISA���x�̉^�p�͊����̓������i�̔������x�����Ƃɍs���Ă��邽�߁AiDeCo�̂悤�ȉ������萔���E�����Ǘ��萔���E��掞�萔���Ȃǂ̒�߂�����܂���B���Ƃ��ƌ����萔���Ȃǂ����Ă��Ȃ����Z�@�ւł���ANISA�����ɂ�����萔���͖����ł��B���Ƃ͋��Z���i�̏���̔����萔����A�����M���̏ꍇ�͐M����V�Ȃǂ̎萔������OK�ł��B����ɁA�l�b�g�،��Ȃǂ̋��Z�@�ւ̂Ȃ��ɂ͔̔����i�̂��߂ɁANISA�����ł̋��Z���i�̔����萔���������ɂ��Ă���ꍇ������܂��B
�C�@�݂���NISA�����NISA���ǂ��炩��I�Ԃ��Ƃ��ł���
������x�]�T����������l�⊔���ɓ����������l�͈��NISA�A���ꂩ�玑���Â�����������l�ʼn^�p���i�͓����M���ł����܂�Ȃ��l�݂͂���NISA�Ƃ����悤�ɁA�X�l�̃P�[�X�ɉ����Ăǂ��炩��I�����邱�Ƃ��ł��܂��B
iDeCo�Ɣ�r�����uNISA�v�̃f�����b�g
�@�@���Ԍ���̐��x�ł���
���NISA��2014�N�`2023�N�A�݂���NISA��2018�N�`2037�N�̊��Ԍ���̔�ېŐ��x�ł��i���NISA��2023�N�ɍw���������Z���i�̉^�p�v��5�N�ڂ�2027�N�܂ŁA�݂���NISA��2037�N�ɍw���������Z���i�̉^�p�v��20�N�ڂ�2056�N�܂Ŕ�ېŁj�B���ɁA���NISA���I�����Ă��܂��ƁA���Ƃ݂͂���NISA��iDeCo�̂悤�Ȑϗ��^�̔�ېŐ��x�����c��Ȃ����ߕs�ւł��B
�����������2018�N9�����݂̘b�ł��BNISA���D���ȏꍇ�́A���������Ȃǂ̑[�u�������\��������܂��B
�A�@���Z���i�w�����ɐŖ@��̗D�����Ȃ�
NISA�̉^�p���i�w�����̎����ɂ́AiDeCo�̂悤�Ȋ|�����o���̊|���S�z�����T���Ƃ������Ŗ@��̗D���͂���܂���B�����܂ł��ӂ��̎��Ȏ����ł̓����Ƃ����ʒu�Â��ł��B���̑���AiDeCo�̂悤�ɉ^�p������掞�ɏ����Ƃ��ĉېőΏۂɂȂ邱�Ƃ�����܂���B���p����͉^�p�v�ɐŋ��������邱�ƂȂ��A���̂܂�邱�Ƃ��ł��܂��B
�ȏ�̂悤�ɁAiDeCo�A���NISA��݂���NISA�ɂ̓����b�g�E�f�����b�g������܂��BiDeCo��I�Ԃ�NISA��I�Ԃ��́A�����̃����b�g�E�f�����b�g���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����̌�҂ł́A�����x�̃����b�g�E�f�����b�g�ɂ��ƂÂ��āAiDeCo���g�N�ȃP�[�X�ANISA�������Ă���P�[�X�ȂǁA�P�[�X�ʂɂ��Љ�܂��B
�֘A�y�[�W
���ЂƂ肳�܂̘V��
 �s���ɏZ�ރV���O�������̉�Ј��A�ē����Ƃ݂���i35�A�����j�͎���25���~�̎����A���݃}���V�����i�ƒ�7���~�j�łЂƂ��炵�����Ă��܂��B�܂�������������߂��킯�ł͂���܂��A���ꂩ��̐l�����ЂƂ�ŕ��މ\�����l���V��̌v��𗧂Ă邱�Ƃɂ��܂����B�V��ɕK�v�Ȑ�����܂��͘V��ɕK�v�Ȑ����...
�s���ɏZ�ރV���O�������̉�Ј��A�ē����Ƃ݂���i35�A�����j�͎���25���~�̎����A���݃}���V�����i�ƒ�7���~�j�łЂƂ��炵�����Ă��܂��B�܂�������������߂��킯�ł͂���܂��A���ꂩ��̐l�����ЂƂ�ŕ��މ\�����l���V��̌v��𗧂Ă邱�Ƃɂ��܂����B�V��ɕK�v�Ȑ�����܂��͘V��ɕK�v�Ȑ����...
���ۂ̂Ƃ���N���͂�������炦��́H
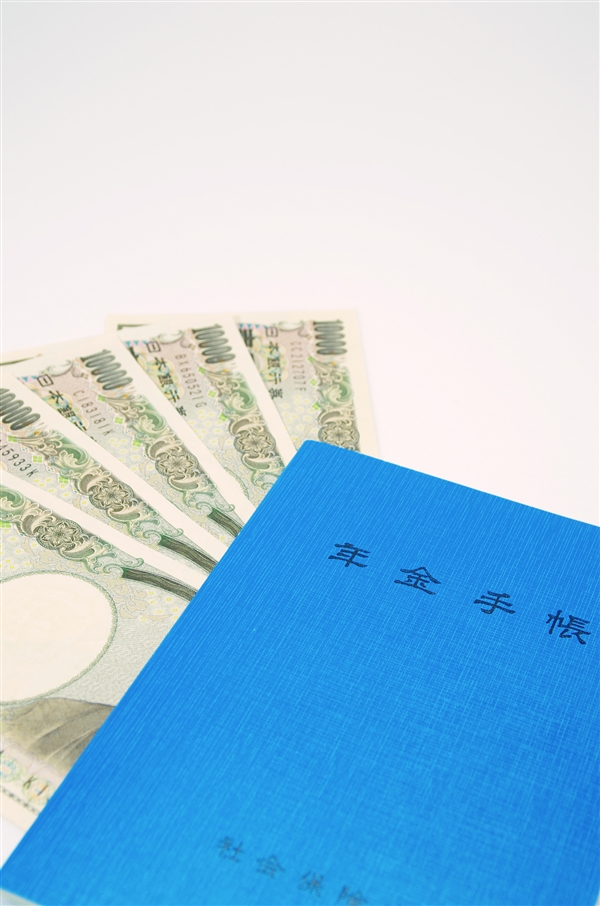 �N���̎��z��m�낤�݂Ȃ��܂͎������V��ɂȂ����Ƃ��A�N����������Ⴆ�邩�����m�ł��傤���B���R�Ǝ����20���~���炢�͖Ⴆ��̂��ȁ`�Ƃ��A���₢��30���͖��Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��Ƃ��A���҂�s��������܂���ˁB���m�ȔN���̋��z���o�����Ƃ���ƕ��G�Ȃ̂ł����A��܂��Ȋz�͂��������������邱�Ƃ��ł�...
�N���̎��z��m�낤�݂Ȃ��܂͎������V��ɂȂ����Ƃ��A�N����������Ⴆ�邩�����m�ł��傤���B���R�Ǝ����20���~���炢�͖Ⴆ��̂��ȁ`�Ƃ��A���₢��30���͖��Ȃ��Ƃ���Ă����Ȃ��Ƃ��A���҂�s��������܂���ˁB���m�ȔN���̋��z���o�����Ƃ���ƕ��G�Ȃ̂ł����A��܂��Ȋz�͂��������������邱�Ƃ��ł�...
�N�����������ی�̕������Ȃ�ł����H
 �{���ɔN�����������ی�̕������Ȃ̂ł��傤���O��A���ۂɎ��N���̎z�͎v�����������Ȃ��Ƃ������b�����܂����B���t�{�̒����ɂ��ƁA�N���ŕ�炵�Ă��鍂��҂�5�l��1�l�͐����ی�ȉ��̔N�������ŕ�炵�Ă���̂������ł��B�������A���̊����͍���܂��܂����܂��Ă������Ƃ��\�z����Ă���̂ł��B...
�{���ɔN�����������ی�̕������Ȃ̂ł��傤���O��A���ۂɎ��N���̎z�͎v�����������Ȃ��Ƃ������b�����܂����B���t�{�̒����ɂ��ƁA�N���ŕ�炵�Ă��鍂��҂�5�l��1�l�͐����ی�ȉ��̔N�������ŕ�炵�Ă���̂������ł��B�������A���̊����͍���܂��܂����܂��Ă������Ƃ��\�z����Ă���̂ł��B...
���ϔN���ʂ̘V�㎎�Z�ɂ���
 �����N���⍑���N���́A�V��̐������x����厖�Ȏ������ł��B���������͂ǂ̂��炢���炦�邾�낤���ƋC�ɂȂ�܂��B�N�������Ő����ł��Ȃ��ƂȂ�A�s������₤���߂̒��~���K�v�ł��B�����N���⍑���N���̎z�A�����Ă��ЂƂ肳�܂̘V��̐����ɕK�v�ƂȂ钙�~�ڈ��ϔN��300���~�A400���~�A500��...
�����N���⍑���N���́A�V��̐������x����厖�Ȏ������ł��B���������͂ǂ̂��炢���炦�邾�낤���ƋC�ɂȂ�܂��B�N�������Ő����ł��Ȃ��ƂȂ�A�s������₤���߂̒��~���K�v�ł��B�����N���⍑���N���̎z�A�����Ă��ЂƂ肳�܂̘V��̐����ɕK�v�ƂȂ钙�~�ڈ��ϔN��300���~�A400���~�A500��...
�y�N��ʁz�V�㎑���̏����ɂ��ċ����Ă�������
 �V��̒������Ԃ͑����̐l�ɖK��܂����A�Ⴏ��ΎႢ�قnj��������N���Ȃ����Ƃ������B�����̗��e��c�����g�߂Ɍ��Ē��~�̕K�v���������Ă���l������A�����ɂ��邽�߂Ɏ����̖����Əd�˂邱�Ƃ��ł����A�����l��������Ɛ扄���ɂ���l������ȂǁA�l��������܂��B�������A�V��̔����͑����n�߂��ق�����...
�V��̒������Ԃ͑����̐l�ɖK��܂����A�Ⴏ��ΎႢ�قnj��������N���Ȃ����Ƃ������B�����̗��e��c�����g�߂Ɍ��Ē��~�̕K�v���������Ă���l������A�����ɂ��邽�߂Ɏ����̖����Əd�˂邱�Ƃ��ł����A�����l��������Ɛ扄���ɂ���l������ȂǁA�l��������܂��B�������A�V��̔����͑����n�߂��ق�����...
�l�N���͕K�{�ł�
 ���I�N�������ł͂��т������ЂƂ肳�܂̘V��ɂ�����悤�ɔN�����������ł͘V��̐����͂ƂĂ����т������̂ɂȂ�܂��B�V��̑������������O����钆�A���I�N���Ƀv���X���ĘV��̐������J�o�[���閯�Ԃ̌l�N���͂��͂�K�{�̔����Ƃ����܂��B�V��̔����͎茘������ׂ��悭�A�l�N���͗���肪�����Ƃ��C���t���Ɏ�...
���I�N�������ł͂��т������ЂƂ肳�܂̘V��ɂ�����悤�ɔN�����������ł͘V��̐����͂ƂĂ����т������̂ɂȂ�܂��B�V��̑������������O����钆�A���I�N���Ƀv���X���ĘV��̐������J�o�[���閯�Ԃ̌l�N���͂��͂�K�{�̔����Ƃ����܂��B�V��̔����͎茘������ׂ��悭�A�l�N���͗���肪�����Ƃ��C���t���Ɏ�...
�l�N���͂�����K�v�ł����H
 ���ώ��������ё����钆�A�V��̐����ɕs���������Ă���l�͑������܂��B�V��̌��I�N���̎z�����ł͐��������Ȃ������ƐS�z���A�ǂ��������炢���̂��낤�ƔY��ł��܂��B���̎�i�̈�Ƃ��Čl�N�����C�ɂȂ�l������ł��傤�B���p����ꍇ�ɁA�ǂ̂��炢�̕ی������K�v�Ȃ̂��A�����b�g��f�����b�g�Ȃ�...
���ώ��������ё����钆�A�V��̐����ɕs���������Ă���l�͑������܂��B�V��̌��I�N���̎z�����ł͐��������Ȃ������ƐS�z���A�ǂ��������炢���̂��낤�ƔY��ł��܂��B���̎�i�̈�Ƃ��Čl�N�����C�ɂȂ�l������ł��傤�B���p����ꍇ�ɁA�ǂ̂��炢�̕ی������K�v�Ȃ̂��A�����b�g��f�����b�g�Ȃ�...
�l�N���͒������ɔ�����ی�
 �l�N���Ƃ͌l�N���ی��Ƃ́A���Ԃ̕ی���Ђ��̔�����ی����i�̂��Ƃł��B�����ی������x�������ƂŌ_�ɒ�߂��N�������z�̔N�����x������d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��B���I�N���̕s����₤���߂̘V�㎑���Ƃ��Č��������̂���ʓI�ł��B�l�N���͕K�v�H�V��̔����Ɍl�N���̓}�X�g�ƍl���Ă悢�ł��傤�B...
�l�N���Ƃ͌l�N���ی��Ƃ́A���Ԃ̕ی���Ђ��̔�����ی����i�̂��Ƃł��B�����ی������x�������ƂŌ_�ɒ�߂��N�������z�̔N�����x������d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��B���I�N���̕s����₤���߂̘V�㎑���Ƃ��Č��������̂���ʓI�ł��B�l�N���͕K�v�H�V��̔����Ɍl�N���̓}�X�g�ƍl���Ă悢�ł��傤�B...
�����ی������l�N��
 �����Đ����ی��ɓ���K�v�͂Ȃ��ł��������������ی��͎c���ꂽ�Ƒ��̐�����ۏႷ�邽�߂ɕK�v�ȕی��ł��B���ЂƂ肳�܂̏ꍇ�͎��g�̑��V��p��300���~���x�K�v�Ƃ������Ƃœ����Ă���������邱�Ƃł��傤�B�������A���̒��x�̕ۏ���z�ł���Όl�N���ɕt�����Ă��܂����A�Z��[����g�ꍇ�͒c�̐����ی���...
�����Đ����ی��ɓ���K�v�͂Ȃ��ł��������������ی��͎c���ꂽ�Ƒ��̐�����ۏႷ�邽�߂ɕK�v�ȕی��ł��B���ЂƂ肳�܂̏ꍇ�͎��g�̑��V��p��300���~���x�K�v�Ƃ������Ƃœ����Ă���������邱�Ƃł��傤�B�������A���̒��x�̕ۏ���z�ł���Όl�N���ɕt�����Ă��܂����A�Z��[����g�ꍇ�͒c�̐����ی���...
�ی��̌������͕K�v�ł����H
 ���Ȃ��́A�����������Ă��鐶���ی��̕ی�����c���ł��Ă��܂����B���N������������ی������ƌv�ɗ^����e���͏������Ȃ��ɂ�������炸�A�ۏ���e���悭�������Ă��Ȃ���Ԃŕی���Ђ̐l�Ɋ��߂���܂܌_�Ă��܂����Ƃ����l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ی��́A���C�t�X�e�[�W���ƂɓK�ƂȂ�v�������ς�...
���Ȃ��́A�����������Ă��鐶���ی��̕ی�����c���ł��Ă��܂����B���N������������ی������ƌv�ɗ^����e���͏������Ȃ��ɂ�������炸�A�ۏ���e���悭�������Ă��Ȃ���Ԃŕی���Ђ̐l�Ɋ��߂���܂܌_�Ă��܂����Ƃ����l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ی��́A���C�t�X�e�[�W���ƂɓK�ƂȂ�v�������ς�...
�u2025�N���v�ɂ��čl����
 �X���������҂̊����������A����Љ�Ŋ�����悤�ɂȂ�܂����B�������A���{�̍�����������̘V��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ǝ����ł��Ă���l�͈ӊO�Ə��Ȃ������m��܂���B�����I�����s�b�N�̂킸��5�N��ɂ́A2025�N��肪����Ă��܂��B2025�N���Ƃ͉��Ȃ̂��A�ǂ�ȉe��������̂��ɂ��āA�킩���...
�X���������҂̊����������A����Љ�Ŋ�����悤�ɂȂ�܂����B�������A���{�̍�����������̘V��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ǝ����ł��Ă���l�͈ӊO�Ə��Ȃ������m��܂���B�����I�����s�b�N�̂킸��5�N��ɂ́A2025�N��肪����Ă��܂��B2025�N���Ƃ͉��Ȃ̂��A�ǂ�ȉe��������̂��ɂ��āA�킩���...
iDeCo�i�C�f�R�j�ŘV��ɔ�����
 iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j�́A���I�N���i�����N��������N���j�ł͕s������V��̎����������ŏ����ł���悤�Ɏn�߂�ꂽ���I�N�����x�ł��B���ɔC�����ςȂ��̌��I�N����A�ی���ЂɔC�����ςȂ��̌l�N���ی��ƈႢ�AiDeCo�ł͎������g�ŔN�������̉^�p��Ǘ������邱�ƂɂȂ�܂��B�|���͏�����...
iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j�́A���I�N���i�����N��������N���j�ł͕s������V��̎����������ŏ����ł���悤�Ɏn�߂�ꂽ���I�N�����x�ł��B���ɔC�����ςȂ��̌��I�N����A�ی���ЂɔC�����ςȂ��̌l�N���ی��ƈႢ�AiDeCo�ł͎������g�ŔN�������̉^�p��Ǘ������邱�ƂɂȂ�܂��B�|���͏�����...
NISA�i�j�[�T�j�ŘV��ɔ�����
 NISA�i���z������ېŐ��x�j�́A�l�}�l�[���s��ɌĂэ��ނƂƂ��ɁA��ʌl�̒����I�Ȏ��Y�`�����߂����A2014�N����X�^�[�g������ېŐ��x�ł��B�ӂ��Ɋ����Ⓤ���M���ɓ��������ꍇ�A�z�����╪�z���A���p�v��20.315%�̐ŋ���������܂����ANISA���g���Ƃ��̐ŋ���0%�ɂȂ�܂��B���ЂƂ肳��...
NISA�i���z������ېŐ��x�j�́A�l�}�l�[���s��ɌĂэ��ނƂƂ��ɁA��ʌl�̒����I�Ȏ��Y�`�����߂����A2014�N����X�^�[�g������ېŐ��x�ł��B�ӂ��Ɋ����Ⓤ���M���ɓ��������ꍇ�A�z�����╪�z���A���p�v��20.315%�̐ŋ���������܂����ANISA���g���Ƃ��̐ŋ���0%�ɂȂ�܂��B���ЂƂ肳��...
���ǂ̂Ƃ���iDeCo��NISA�ǂ����������́H�i�O�ҁj
 iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j�́A�����N��������N���Ȃǂ̌��I�N����₤���߂ɓ������ꂽ�C�Ӊ����̎��I�N�����x�ł��B����ANISA�i�j�[�T�F���z������ېŐ��x�j�́A�l�}�l�[���s��ɌĂэ��ݎs���������������ƂƂ��ɁA�l�̒����I�Ȏ��Y�`���̂��߂ɃX�^�[�g������ېŐ��x�ł��B�X�^�[�g�����o...
iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j�́A�����N��������N���Ȃǂ̌��I�N����₤���߂ɓ������ꂽ�C�Ӊ����̎��I�N�����x�ł��B����ANISA�i�j�[�T�F���z������ېŐ��x�j�́A�l�}�l�[���s��ɌĂэ��ݎs���������������ƂƂ��ɁA�l�̒����I�Ȏ��Y�`���̂��߂ɃX�^�[�g������ېŐ��x�ł��B�X�^�[�g�����o...
���ǂ̂Ƃ���iDeCo��NISA�ǂ����������́i��ҁj
 iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j��NISA�i�j�[�T�F���z������ېŐ��x�j���A�^�p�v��20.315%�̐ŋ���������Ȃ����Y�^�p���@�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă��܂��B�O�҂ł�iDeCo��NISA���ꂼ��̐��x�̊T�v�ƃ����b�g�E�f�����b�g�ɂ��Ă��������܂����B����̌�҂ł́AiDeCo�E�݂���NISA...
iDeCo�i�C�f�R�F�l�^�m�苒�o�N���j��NISA�i�j�[�T�F���z������ېŐ��x�j���A�^�p�v��20.315%�̐ŋ���������Ȃ����Y�^�p���@�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂Ă��܂��B�O�҂ł�iDeCo��NISA���ꂼ��̐��x�̊T�v�ƃ����b�g�E�f�����b�g�ɂ��Ă��������܂����B����̌�҂ł́AiDeCo�E�݂���NISA...
���ЂƂ肳�܂̉����
 �e�̉��Ǝ����̉�삨�ЂƂ肳�܂̉����ƌ����Ă��A�������g�̉����Ɛe�̉����̂ӂ����l�����܂��B�����A��엣�E���b��ɂȂ�Ȃǐe�̉��������Ēʂ�Ȃ����ɂȂ����܂��B���ЂƂ肳�܂ɂƂ��Ă����̖��͂ǂ̂悤�ɏ��z���Ă����悢�̂ł��傤���B���͑傫���ӂ��l�����܂��B���I��...
�e�̉��Ǝ����̉�삨�ЂƂ肳�܂̉����ƌ����Ă��A�������g�̉����Ɛe�̉����̂ӂ����l�����܂��B�����A��엣�E���b��ɂȂ�Ȃǐe�̉��������Ēʂ�Ȃ����ɂȂ����܂��B���ЂƂ肳�܂ɂƂ��Ă����̖��͂ǂ̂悤�ɏ��z���Ă����悢�̂ł��傤���B���͑傫���ӂ��l�����܂��B���I��...
�ސE��̌��N�ی��͂ǂ�����悢�ł����H
 ��Ђœ����Ă���Ƃ��͓�����O�̂悤�Ɏg���Ă�����Ђ̌��N�ی��B�������A�]�E��^�C�������g�Ȃǂʼn�Ђ�ސE�����Ƃ��́A��Ј�����Ƃ͈Ⴄ�ق��̌��N�ی��ɉ������邱�ƂɂȂ�܂��B���̍ہA�ǂ��������N�ی��̑I����������̂��A�ǂ̌��N�ی��ɉ�������̂����g�N�Ȃ̂��ȂǑސE��̌��N�ی��ɂ��ďڂ��������...
��Ђœ����Ă���Ƃ��͓�����O�̂悤�Ɏg���Ă�����Ђ̌��N�ی��B�������A�]�E��^�C�������g�Ȃǂʼn�Ђ�ސE�����Ƃ��́A��Ј�����Ƃ͈Ⴄ�ق��̌��N�ی��ɉ������邱�ƂɂȂ�܂��B���̍ہA�ǂ��������N�ی��̑I����������̂��A�ǂ̌��N�ی��ɉ�������̂����g�N�Ȃ̂��ȂǑސE��̌��N�ی��ɂ��ďڂ��������...
�ӂ邳�Ɣ[�ł̊m��\���ɂ��ċ����Ă�������
 �u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�́A�����������̂Ɋ����z�ɉ����ď����ł�Z���ł����łɂȂ鐧�x�ł��B�����̎����̂������Ă��ꂽ�l�ɑ��邨��̕i�i�ԗ�i�j�ɁA�u�����n���́v�u���g�N�Ȃ��́v����肻�낦�l�C���W�߂Ă��܂��B�ӂ邳�Ɣ[�ł̑�햡�́A���ł����Ȃ��炱�̕ԗ�i�����炦���Γ̊y���݂ɂ���܂���...
�u�ӂ邳�Ɣ[�Łv�́A�����������̂Ɋ����z�ɉ����ď����ł�Z���ł����łɂȂ鐧�x�ł��B�����̎����̂������Ă��ꂽ�l�ɑ��邨��̕i�i�ԗ�i�j�ɁA�u�����n���́v�u���g�N�Ȃ��́v����肻�낦�l�C���W�߂Ă��܂��B�ӂ邳�Ɣ[�ł̑�햡�́A���ł����Ȃ��炱�̕ԗ�i�����炦���Γ̊y���݂ɂ���܂���...