���ЂƂ肳�܂̃}�l�[�v��������`iDeCo�ŘV�㎑�Y���`�����悤�`

�͂��߂�
���݁A���{�͋}���ɐi�ޏ��q�����w�i�Ƃ��Č��I�N�����x�̊�Ղ��h�炬�A�V��s������u�V���v�Ƃ������t����ь����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂����́A��������̎���ł�����A��s�ɂ�����a���Ă��Ă��A���Y�������Ă������Ƃ����҂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂�����ł��B
�����āA���{���f����u���~���瓊���ցv�̃X���[�K���̂��ƁA���܁A�����͎����w�͂ɂ���Ď��Y�`�����s���Ă������Ƃ����߂��Ă��܂��B
���̂悤�ȎЉ��̂Ȃ��A2017�N1������A��{�I��60�Ζ����̂��ׂĂ̐l��iDeCo�ɉ����ł���悤�ɂȂ�܂����B
�����ō���́A�L���ȘV��𑗂邽�߂�iDeCo�̊��p�Ɋւ��āA���̌o�ϓI�E�Љ�I�Ȕw�i����������Ɣc������ƂƂ��ɁAiDeCo�̎d�g�݂⊈�p����ۂ̒��ӓ_�Ȃǂ��ڂ���������Ă����܂��B
���{�̌o�ώЉ���c�����悤
�Ȃ��A�L���ȍ��ł������͂��̓��{�ŁA�������炪�V�㎑�Y�̌`�����s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��傤���B�܂��͂��̋^��ɓ�����ׂ��A���݂̓��{���u���ꂽ�o�ρE�Љ����ȒP�ɔc�����Ă����܂��傤�B
�܂��A���̓��{�ɂ͘V��s�������܂Ƃ��Ă��܂��B�}���ɐi�ލ���ɂ��A�Љ�ۏ��͖c��オ�荑�̍������������Ă��܂��B�F������N���͌��z�����\�����������A�����R�X�g�͑傫���ς��Ȃ������݂ł��B���̂��߁A���I�N�������ł͖L���ȘV��𑗂邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă���Ƃ�����ł��傤�B
�����A���̃f�[�^����������������A����̐����������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
����28�N�x�����݁A�����N���������V��N���̕��ό��z��5��5��~�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���Ԋ�Ƃ̉�Ј��Ȃǂ��Ώۂ̌����N���i��P���j�������N���̕��ό��z�́A 14 ��6��~�ƂȂ��Ă��܂��B
����ŁA�v�w2�l�ŘV�㐶���𑗂��ŕK�v�ƍl������Œ�̓��퐶����͌��z22���~�A��Ƃ肠��V��𑗂�ꍇ��35���~���K�v�Ƃ����������ʂ��o�Ă���܂��B�L���ȘV��𑗂邽�߂ɂ́A�����N��������N���Ƃ��������I�N���ɉ����āA�����w�͂ŘV�㎑�Y���`�����Ă������Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ��f����ł��傤�B
�܂����݂́A���{�̋��Z�V�X�e�����i����{��s���o�ς����x�����邽�ߒ��������������{���Ă��܂��B���̂��ߋ�s�̗a�����������j�I�Ȓᐅ���ƂȂ��Ă��܂��B��������܂��ƁA���K�o���N�̂ЂƂł���O�HUFJ��s�̕��ʗa���̋����͔N0.001���ł��B����1,000���~��a�������Ƃ��Ă��A�N��100�~�̗����������܂���B
�L���ȘV��𑗂邽�߂ɂ́A���I�N���ɉ����ĉ��炩�̎��Y�^�p���K�v�ƂȂ��Ă��܂����A��s�̕��ʗa���ł́A�����ȘV�㎑�Y�̌`���͊��҂ł��Ȃ��Ƃ�����ł��傤�B�����������Ă������Ƃ������Ј������łȂ��A�ސE�蓖��N�������z�����������ȂǂɂƂ��Ă��A�ۂ����ł������w�͂ŘV�㎑�Y���`�����Ă����K�v�ɔ����Ă��܂��B
�����ŁA�������߂��鎑�Y�^�p��i��iDeCo�ł��B�������炻�̓����Ȃǂ��ڂ���������Ă����܂��B
iDeCo�̓�����m�낤
�L���ȘV�㎑�Y���`�����Ă������߂̎��Y�^�p��i�Ƃ��āAiDeCo�͂܂��ɑł��Ă��̋��Z���i�ł��B
iDeCo�͎����w�͂ɂ���Ď��Y�`����}�鎄�I�N�����x�ł��B���̂��߁A�����ł��������o���A���炻�̊|�����^�p���܂��B�����Č����A60�Έȍ~�ɂ���܂Őςݗ��Ă����Y��������d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��B
iDeCo�͋��������ł͂Ȃ��A�����܂ŔC�Ӊ����̐��x�ł���A�����N��������N���̂悤�ɁA�����Ƃ��^�p���F����ɑ����čs���Ă����킯�ł͂���܂���B�����ʼn^�p���鏤�i�����߂Ă������ƂɂȂ�܂��B
�����āAiDeCo�̍ő�̃����b�g�́A�ϗ����E�^�p���E��掞�̂R�i�K�ł̐ߐŌ��ʂ��邱�Ƃł��B
�܂��ϗ����ɂ́A�F���x�����|���̑S�z�������T���̑ΏۂƂȂ�A�����ŁE�Z���ł�ߐł��邱�Ƃ��ł��܂��B���̂��߁A�����ɂ����܂����A�|������������̕������ߐŌ��ʂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
���ɉ^�p���ɂ́A�ʏ�A����a���̗��q�Ⓤ���M���̏��n�v�Ȃǂɂ�����20.315���̐ŋ���������܂���B
���Ƃ��AiDeCo�œ����M���ɓ���������20,000�~�̗��v���������Ƃ��܂��B�ʏ�ł���4,063�~�̐ŋ���������A�茳�ɂ�15,937�~�����c��܂��AiDeCo�͔�ېł̂���20,000�̗��v�����̂܂c��܂��B�܂��A��ېłŕ����������ē����ɉΎ��Y���傫�������Ă����\��������܂��B
������3�i�K�ڂ̎�掞�ɂ��Ő��D��������܂��BiDeCo�ł͌���60�Έȍ~�ɐςݗ��Ă������Y���A�N����ꎞ���Ƃ��āA�������͂����p���邱�ƂŎ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�N���Ƃ��Ď��ꍇ�́A���I�N�����T���̑ΏۂƂȂ�A65�Ζ������ƌ��I�N���Ȃǂ̎�����70���~�܂ŁA65�Έȏゾ��120���~�܂Ŕ�ېłƂȂ�܂��B
�ꎞ���Ƃ��Ď��ꍇ�́A�ސE�����T���̑ΏۂƂȂ�܂��B�T���z�̌v�Z���@�͉��L�̂悤�ɂȂ�܂��B�Ȃ��AiDeCo�ł͋��o���̐ϗ����Ԃ��Α��N���ƌĂт܂��B
�Α��N���i�ϗ����ԁj��20�N�ȉ��@�@40���~ �~ �Α��N���i80���~�ɖ����Ȃ��ꍇ�́A80���~�j
�Α��N����20�N���@�@�@800���~ �{ 70���~ �~�i�Α��N�� �| 20�N�j
���Ƃ��A�Α��N����30�N�̏ꍇ�A�ސE�����T���z��1,500���~�܂Őŋ���������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�܂��AiDeCo�̊|����5,000�~�ȏ�1,000�~�P�ʂŋ��o���邱�Ƃ��ł��A���z����n�߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��E�ƂȂǂɂ���ċ��o���x�z����߂��Ă��܂��B��̓I�ɂ͉��L�̈ꗗ�\���������������B
| �Ώێ� | ���o���x�z�^�� |
|---|---|
| ���c�� | 6.8���~ |
| ������ | 1.2���~ |
| ��Ј��i��ƌ^DC����j | 2.0���~ |
| ��Ј��i�m�苋�t�^�N���j | 1.2���~ |
| ��Ј��i��ƔN���Ȃ��j | 2.3���~ |
| ��Ǝ�w�̕v | 2.3���~ |
����܂�iDeCo�̓��������`�����Ă��܂������A���������iDeCo���n�߂�ɂ����蒍�ӂ��ׂ��_�A3�_���m�F���Ă����܂��傤�B
iDeCo�̒��ӓ_��m�낤
�܂�iDeCo�ɉ�������Ƃ��ɂ́AiDeCo�̉^�c�����ƂȂ���Z�@�ւ��������g�őI�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B�����āA�������Z�@�ւɁu�^�c�Ǘ��萔���v�Ƃ��������Ǘ������x�����܂��B���̉^�c�Ǘ��萔���͋��Z�@�ւɂ���ĈقȂ��Ă��Ă���A�Ⴂ�Ƃ���ł��ƌ��z167�~�Ƃ���Ƃ��������A500�~�ȏシ��Ƃ��������܂��B
iDeCo�͘V�㎑�Y�̌`����ړI�Ƃ��邽�߁A���Y�^�p�������ɂ킽��܂��B���̂��߁A���̂悤�ȃR�X�g�͋ɗ͒Ⴍ�}���邱�Ƃ��]�܂����ł��傤�B����iDeCo�̋��Z�@�֑I�т̈�̕������Ƃ��Ă݂Ă��������B
�܂����ӂ��ׂ��_��2�_�ڂƂ��āAiDeCo�́A��{�I��60�܂Őςݗ��ĂĂ������Y����邱�Ƃ͂ł��܂���B���̂��߁A�}篎q���̋����ɏ[�Ă����Ƃ��A�C�O���s�����ɂ܂킵�����Ƃ����Ă��A�r����Ď����������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��傤�B
���������̓_�Ɋւ��ẮA����Ԃ��ƁA60�܂ł����������o���Ȃ��킯�ł��̂ŁA���~�����Ȑl�ɂƂ��ẮA�v��I�ɘV�㎑�Y���`�����Ă�����d�g�݂ɂȂ��Ă���Ƒ����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�����Ē��ӓ_��3�ڂ́AiDeCo�̍ő�̃����b�g��1�ł��鋒�o���̏����T�����邽�߂ɁA�m��\���̎葱�����s���K�v�ƂȂ�l����������Ⴂ�܂��B
��Ј���������̏ꍇ�A��{�I�ɋΖ����Ƃ��N���������s�����Ƃɂ��AiDeCo�̏����T�����邽�߂̎葱���͏I���ƂȂ�܂��B
����Ŏ��c�Ǝ҂Ȃǂ͔N���������Ȃ����߁A�m��\�������邱�Ƃŏ����T�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
��������Ƃ����葱�����@�����`�����܂��ƁAiDeCo�̉^�c���i�鍑���N������A����疈�N10������11�����炢�Ɂu���K�͊�Ƌ��ϓ��|�������ؖ����v�������Ă��܂��B���̏ؖ����ɂ́A����1�N�Ԃɂ����g�x���������o���v���z���L�ڂ���Ă��܂��B�Ȃ��AiDeCo�̊|���́u���K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���v�Ƃ������ڂŏ����T�����邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA��������Ɗo���Ă����܂��傤�B
�����ŁA�Ŗ�����������m��\�����̏��K�͊�Ƌ��ϓ��|���T���̍��ڂɁA���̔N�̋��o���v���z���L�ڂ��܂��B�����āA�K�v�������L�ڂ����m��\�����Ə��K�͊�Ƌ��ϓ��|�������ؖ������NJ��̐Ŗ����֒�o���邱�Ƃɂ��I���ƂȂ�܂��B
�Ȃ��A�葱���Ɋւ��ĕs���ȓ_�́A�Ŋ��̐Ŗ����ȂǂŊm�F���āA���m�Ɋm��\�������쐬���܂��傤�B
iDeCo�����p���ĘV�㎑�Y���`�����悤�I�I
����܂�iDeCo�����߂���o�ϓI�E�Љ�I�Ȕw�i����AiDeCo�̓����⒍�ӓ_�����Ă��܂����B
�����Ă�������́AiDeCo�̋�̓I�Ȏn�ߕ��₿����Ƃ����|�C���g�����Љ�Ă����܂��B
�����J�ݎ��̂̓C���^�[�l�b�g���玑�������A�K�v�������L�ڂ̂����ԐM���闬��ƂȂ�܂��B�Ȃ������N������A����ł̉������i�Ȃǂ̐R��������A�葱�������܂�2�����قǂ�����ꍇ������܂��B�܂��AiDeCo���n�߂邤���Ŏ葱����̃|�C���g��3�_���`�����܂��B
�@���Z�@�ւ����߂�
�܂���iDeCo�ɉ�������ہA�������g�ŋ��Z�@�ւ�I�����܂��B��قǂ��`�����܂����ʂ�A�u�^�c�Ǘ��萔���v���Ⴂ�Ƃ���ŁA��p��}���Ďn�߂܂��傤�B
�A���o������z�����߂�
���ɋ��o������z�́A�ƌv�Ƒ��k���Ė����̂Ȃ��͈͂Ōp�������邱�ƂɎ��������܂��傤�B
�B�^�p���鏤�i�����߂�
�����āA���Z�@�ւɂ���čw���ł���^�p���i���قȂ��Ă��܂��B��ʓI�ɁA���{�m�ی^�̒���a����ϋɓI�Ƀ��X�N���Ƃ�ɂ������������M���ȂǕ��L���^�C�v�̏��i����葵�����Ă��܂��B���������Z�@�ւɂ���ẮA����ނ̂ݏ��i����Ă���Ƃ��������܂��̂ŁA���Z�@�ւ����߂�ۂɂ��킹�Ċm�F���܂��傤�B
�Ȃ��A�}�Ɏ��ȐӔC�Ŏ��Y�^�p�����邱�Ƃɕs��������l�́A�\�����݂̋��Z�@�ւɂǂ̂悤�ɉ^�p���i��I��ł����悢���A�h�o�C�X�����炤�悤�ɂ��Ă��������B
�Ō�ƂȂ�܂����AiDeCo�̃����b�g�E���ӓ_����������Ɣc�����������ŁA�L���ȘV��𑗂邽�߂̎��Y�`����}��ׂ��AiDeCo�𑶕��Ɋ��p���Ă����܂��傤�B
�s�o�T�t
���t�{�@����29�N�ō���Љ���i�T�v�Łj
�����J���ȔN���ǁ@����28�N�x �����N���ی��E�����N�����Ƃ̊T��
�����ی������Z���^�[�@����28�N�x �����ۏ�Ɋւ��钲�� �s����Łt
�O�HUFJ��s�@�~�a������
�����N������A���� iDeCo�����T�C�g
iDeCo�i�r�@�l�^�m�苒�o�N���i�r
�֘A�y�[�W
���ЂƂ肳�܂̃}�l�[�v��������
 �͂��߂Ɍ��݁A���{�͋}���ɐi�ޏ��q�����w�i�Ƃ��Č��I�N�����x�̊�Ղ��h�炬�A�V��s������u�V���v�Ƃ������t����ь����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂����́A��������̎���ł�����A��s�ɂ�����a���Ă��Ă��A���Y�������Ă������Ƃ����҂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂�����ł��B�����āA���{���f����u���~���瓊���ցv...
�͂��߂Ɍ��݁A���{�͋}���ɐi�ޏ��q�����w�i�Ƃ��Č��I�N�����x�̊�Ղ��h�炬�A�V��s������u�V���v�Ƃ������t����ь����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂����́A��������̎���ł�����A��s�ɂ�����a���Ă��Ă��A���Y�������Ă������Ƃ����҂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂�����ł��B�����āA���{���f����u���~���瓊���ցv...
���ЂƂ肳�܂�FX��������
 �͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A��̊C�O���s��p�Ȃlj������m�ȖړI�̂��߂�FX�������������Ă���l������������Ǝv���܂��B�������́AFX�����ʼn������̗��v��������g���[�_�[�̘b�����������āA������FX�����ő傫���҂������ƒW���v��������Ă���l������������ł��傤�B�����ō���́A���ꂩ��FX�������n...
�͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A��̊C�O���s��p�Ȃlj������m�ȖړI�̂��߂�FX�������������Ă���l������������Ǝv���܂��B�������́AFX�����ʼn������̗��v��������g���[�_�[�̘b�����������āA������FX�����ő傫���҂������ƒW���v��������Ă���l������������ł��傤�B�����ō���́A���ꂩ��FX�������n...
���ЂƂ肳�܂̊�����������
 �͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A�������҂��f�C�g���[�_�[�����f�B�A�ɘI�o����̂����āA�W�����҂��犔���������n�߂悤�ƌ�������Ă���l������������Ǝv���܂��B���̈���ŁA���������Ƃ����ƃM�����u���̂悤�ȁA���X�N�������댯�Ȃ��̂Ƃ��������R�Ƃ����C���[�W�������A���������ɋ����͂�����̂̓�̑���ł�...
�͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A�������҂��f�C�g���[�_�[�����f�B�A�ɘI�o����̂����āA�W�����҂��犔���������n�߂悤�ƌ�������Ă���l������������Ǝv���܂��B���̈���ŁA���������Ƃ����ƃM�����u���̂悤�ȁA���X�N�������댯�Ȃ��̂Ƃ��������R�Ƃ����C���[�W�������A���������ɋ����͂�����̂̓�̑���ł�...
���ЂƂ肳�܂̃e�N�j�J�����͓���
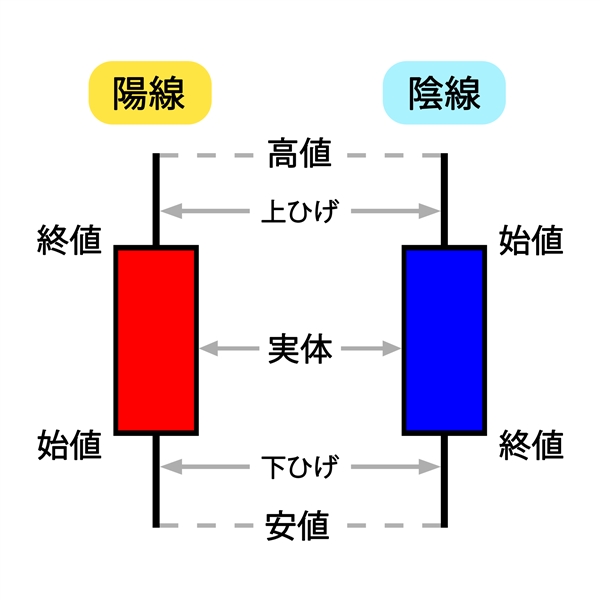 �͂��߂�FX�̐��E�ł͐��b���琔���Ō��Ⴂ�̗��v��������l�����܂��B����ŁA�������炢�̎��Ԃő����o���l�����܂��BFX�����̃x�e���������S�҂������悤�ɁA�e�N�j�J���w�W���g���[�h�Ɋ������Ă��邱�Ƃ������ł��傤�B�����āAFX���M�����u���̂悤�Ƀg���[�h����l�͕ʂƂ��āAFX�̐��E�ł悭�g����̂��e...
�͂��߂�FX�̐��E�ł͐��b���琔���Ō��Ⴂ�̗��v��������l�����܂��B����ŁA�������炢�̎��Ԃő����o���l�����܂��BFX�����̃x�e���������S�҂������悤�ɁA�e�N�j�J���w�W���g���[�h�Ɋ������Ă��邱�Ƃ������ł��傤�B�����āAFX���M�����u���̂悤�Ƀg���[�h����l�͕ʂƂ��āAFX�̐��E�ł悭�g����̂��e...
���ЂƂ肳�܂̃t�@���_�����^�����͓���
 �͂��߂�FX�g���[�h������l�̂Ȃ��ɂ́A�t�@���_�����^���Y���͂����e�N�j�J�����͂���g���ăg���[�h���s���l�������Ǝv���܂��B�����炭���̗��R�́A�t�@���_�����^���Y���͂͂����Ɉב֑���֔��f����Ȃ�����ŁA�e�N�j�J�����͔͂�r�I�Z���ŋ@�\���₷�����͎�@�ł��邱�Ƃ��傫�ȗv���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂�...
�͂��߂�FX�g���[�h������l�̂Ȃ��ɂ́A�t�@���_�����^���Y���͂����e�N�j�J�����͂���g���ăg���[�h���s���l�������Ǝv���܂��B�����炭���̗��R�́A�t�@���_�����^���Y���͂͂����Ɉב֑���֔��f����Ȃ�����ŁA�e�N�j�J�����͔͂�r�I�Z���ŋ@�\���₷�����͎�@�ł��邱�Ƃ��傫�ȗv���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂�...
���ЂƂ肳�܂̓����M������
 �͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A��s�ɗa���Ă��Ă��A�Ȃ��Ȃ����Y�������Ă����Ȃ����߁A��������ƒ����ɉ^�p���铊���M���ւ̓������������Ă���l������������Ǝv���܂��B�����Ƌ�̓I�ɁA�q���̋��玑����Z��w�������ɂ��Ă邽�߁A�����M���֓��������Ď��Y�`����}�낤�ƍl���Ă���l�����邱�Ƃł��傤�B�����͌���...
�͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A��s�ɗa���Ă��Ă��A�Ȃ��Ȃ����Y�������Ă����Ȃ����߁A��������ƒ����ɉ^�p���铊���M���ւ̓������������Ă���l������������Ǝv���܂��B�����Ƌ�̓I�ɁA�q���̋��玑����Z��w�������ɂ��Ă邽�߁A�����M���֓��������Ď��Y�`����}�낤�ƍl���Ă���l�����邱�Ƃł��傤�B�����͌���...
���ЂƂ肳�܂̉��z�ʉݓ���
 ������̌��ώ�i�Ƃ��Ċ��҂���鉼�z�ʉ݂́A���̉��l�̏㏸�ɂ�蓊����Ƃ��Ă����ڂ����悤�ɂȂ�܂����B�r�b�g�R�C���̋}���ʼn��z�ʉ݂ɋ������������l�������ł��傤�B�������A���z�ʉ݂ɂ��ďڂ����m�����Ȃ����߂ɁA����ւƂ͓��ݏo���Ă��Ȃ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����ō���́A���ꂩ�牼�z�ʉ�...
������̌��ώ�i�Ƃ��Ċ��҂���鉼�z�ʉ݂́A���̉��l�̏㏸�ɂ�蓊����Ƃ��Ă����ڂ����悤�ɂȂ�܂����B�r�b�g�R�C���̋}���ʼn��z�ʉ݂ɋ������������l�������ł��傤�B�������A���z�ʉ݂ɂ��ďڂ����m�����Ȃ����߂ɁA����ւƂ͓��ݏo���Ă��Ȃ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����ō���́A���ꂩ�牼�z�ʉ�...
���ЂƂ肳�܂̌l����������
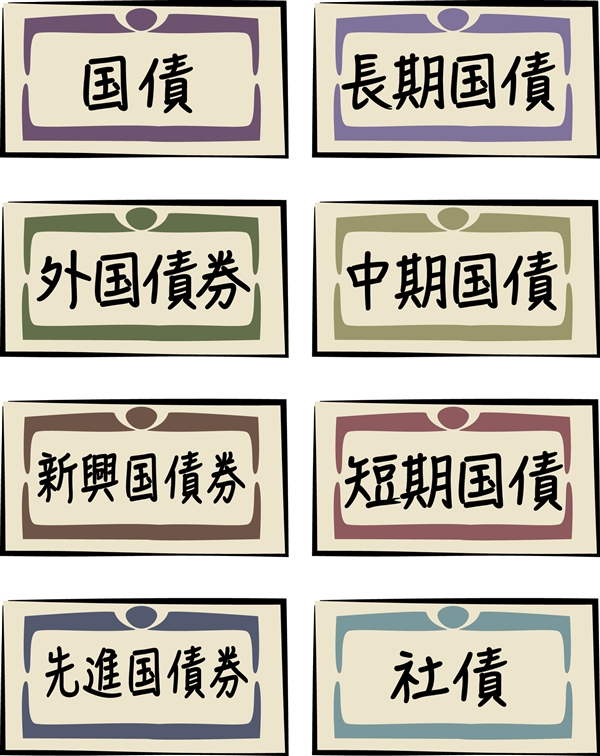 �͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A�Z��w��������V��̔����Ȃǂ̂��߂ɒ��~�����Ă���l�͂�������������Ǝv���܂��B�������A��������̌��݂ł́A��s�ɗa���Ă��Ă����Y�͂قƂ�Ǒ����邱�Ƃ͂���܂���B�����āA�ŋ߃��f�B�A�ł��b��ɂȂ��Ă���u����l�v��y�o���鉼�z�ʉݓ����́A�l����������������n�C���X�N...
�͂��߂ɊF����̂Ȃ��ɂ́A�Z��w��������V��̔����Ȃǂ̂��߂ɒ��~�����Ă���l�͂�������������Ǝv���܂��B�������A��������̌��݂ł́A��s�ɗa���Ă��Ă����Y�͂قƂ�Ǒ����邱�Ƃ͂���܂���B�����āA�ŋ߃��f�B�A�ł��b��ɂȂ��Ă���u����l�v��y�o���鉼�z�ʉݓ����́A�l����������������n�C���X�N...
���ЂƂ肳�܂̌��I�N������
 �͂��߂Ɂu�����F�ی��v���x�̂��ƁA���{�����̂��ׂĂ̐l�����炩�̕ی��ɉ������Ă��܂��B�������A���q�����w�i�Ƃ��āA���{�̎Љ�ۏ�����͂Ђ������Ă��܂��B���̂��߁A��N�w�𒆐S�ɏ����̔N���z�̖ڌ��肪���O����Ă���̂�����ł��B�����ō���́A���������V�㐶�������S�E���肵�ĕ�炷���߂́A���...
�͂��߂Ɂu�����F�ی��v���x�̂��ƁA���{�����̂��ׂĂ̐l�����炩�̕ی��ɉ������Ă��܂��B�������A���q�����w�i�Ƃ��āA���{�̎Љ�ۏ�����͂Ђ������Ă��܂��B���̂��߁A��N�w�𒆐S�ɏ����̔N���z�̖ڌ��肪���O����Ă���̂�����ł��B�����ō���́A���������V�㐶�������S�E���肵�ĕ�炷���߂́A���...
���ЂƂ肳�܂̕s���Y��������
 �����Љ�ۏ�E�l����茤�����ɂ��A�u���{�̐��ѐ��̏������v�v��1�ɂ��ƁA������22�N���2040�N�ɂ͂��悻4���̐��т��u���ЂƂ肳�܁v���тɂȂ�Ɛ�������Ă��܂��B���������u���ЂƂ肳�܁v������������߂ɂ͂ǂ̂悤�ȘV��̎����v��𗧂ĂĂ����悢�̂ł��傤���H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@...
�����Љ�ۏ�E�l����茤�����ɂ��A�u���{�̐��ѐ��̏������v�v��1�ɂ��ƁA������22�N���2040�N�ɂ͂��悻4���̐��т��u���ЂƂ肳�܁v���тɂȂ�Ɛ�������Ă��܂��B���������u���ЂƂ肳�܁v������������߂ɂ͂ǂ̂悤�ȘV��̎����v��𗧂ĂĂ����悢�̂ł��傤���H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@...
�N���W�b�g�J�[�h�̂��𗧂��m��
 ���̋L���ł́A�N���W�b�g�J�[�h�́u������Ɩ𗧂��m���v�I�Ȃ��Ƃ��Љ�Ă��܂��B���i�C�y�Ɏg���Ă���N���W�b�g�J�[�h�A���̋L����ǂ߂����Ɛg�߂Ȃ��̂Ɋ����đ�ɂ��邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł��B�ӊO�ɒm��Ȃ��N���W�b�g�J�[�h���ꂱ��ł��B�N���W�b�g�J�[�h�̎d�g�݃N���W�b�g�J�[�h�Ƃ́A�㕥���Ŕ��������ł�...
���̋L���ł́A�N���W�b�g�J�[�h�́u������Ɩ𗧂��m���v�I�Ȃ��Ƃ��Љ�Ă��܂��B���i�C�y�Ɏg���Ă���N���W�b�g�J�[�h�A���̋L����ǂ߂����Ɛg�߂Ȃ��̂Ɋ����đ�ɂ��邱�ƊԈႢ�Ȃ��ł��B�ӊO�ɒm��Ȃ��N���W�b�g�J�[�h���ꂱ��ł��B�N���W�b�g�J�[�h�̎d�g�݃N���W�b�g�J�[�h�Ƃ́A�㕥���Ŕ��������ł�...
�N���W�b�g�J�[�h�̎�ނɂ���
 �N���W�b�g�J�[�h�̎�ނ͔��ɑ����A�ǂ��I��ł悢�������Ă��܂��܂��B�ł���Ύ����ɂƂ��ē�����J�[�h��I�т������̂ł��B�����ł��̋L���ł́A�N���W�b�g�J�[�h����ޕʂɉ�����A��\�I�ȃJ�[�h���܂Ƃ߂Ă݂܂����B�N���W�b�g�J�[�h�̎�ނƓ��������ɕ��ނ����킯�ł͂���܂��A��ʓI�Ɉȉ��̂悤�ɕ�...
�N���W�b�g�J�[�h�̎�ނ͔��ɑ����A�ǂ��I��ł悢�������Ă��܂��܂��B�ł���Ύ����ɂƂ��ē�����J�[�h��I�т������̂ł��B�����ł��̋L���ł́A�N���W�b�g�J�[�h����ޕʂɉ�����A��\�I�ȃJ�[�h���܂Ƃ߂Ă݂܂����B�N���W�b�g�J�[�h�̎�ނƓ��������ɕ��ނ����킯�ł͂���܂��A��ʓI�Ɉȉ��̂悤�ɕ�...
�u�����h�J�[�h�̍ō���`�A���b�N�X�`
 �A���b�N�X�́A�u�����h�J�[�h�̒��ł��ō���Ɉʒu���Ă��܂��B�A���b�N�X�͋�`���E���W��|�C���g�̃}�C���ւ̌����ȂǁA�C�O���s�Ɋւ�����T���[�����Ă���̂������ł��B���̋L���ł̓A���b�N�X�̓����⑼�Ѝ��ۃu�����h�Ƃ̈Ⴂ�A�J�[�h�̃��C���i�b�v�Љ��v���`�i�J�[�h����܂ł̓��̂�Ƃ�������{�����������...
�A���b�N�X�́A�u�����h�J�[�h�̒��ł��ō���Ɉʒu���Ă��܂��B�A���b�N�X�͋�`���E���W��|�C���g�̃}�C���ւ̌����ȂǁA�C�O���s�Ɋւ�����T���[�����Ă���̂������ł��B���̋L���ł̓A���b�N�X�̓����⑼�Ѝ��ۃu�����h�Ƃ̈Ⴂ�A�J�[�h�̃��C���i�b�v�Љ��v���`�i�J�[�h����܂ł̓��̂�Ƃ�������{�����������...
�f�B�Y�j�[�D���Ȃ�`JCB�`
 JCB�͓��{���̍��ۃu�����h�ŁA���Ƀf�B�Y�j�[�����h�D���̐l�ɂ������߂ł��B���C�Z���X�̔��s�����łȂ��A�v���p�[�J�[�h�����甭�s���Ă���̂�JCB�̑傫�ȓ����ƂȂ��Ă��܂��B���̋L���ł�JCB�̓�����J�[�h�̃o���G�[�V�����A�����ď��Ґ��ł���JCB�U�E�N���X���擾���邽�߂ɒm���Ă��������|�C���g����...
JCB�͓��{���̍��ۃu�����h�ŁA���Ƀf�B�Y�j�[�����h�D���̐l�ɂ������߂ł��B���C�Z���X�̔��s�����łȂ��A�v���p�[�J�[�h�����甭�s���Ă���̂�JCB�̑傫�ȓ����ƂȂ��Ă��܂��B���̋L���ł�JCB�̓�����J�[�h�̃o���G�[�V�����A�����ď��Ґ��ł���JCB�U�E�N���X���擾���邽�߂ɒm���Ă��������|�C���g����...
������������
 ���������̓n�C���X�N�V��̓��W�L���ȂǂŁA���ɐ����~�ł�3%�̗����𑱂���30�N�ςݏグ�Ă����A�V��̎����������ł��܂��Ƃ����L�����������܂��B�������A����Ȃ��Ƃ͐�ɋN���肦�Ȃ��̂ŐM���Ă͂����܂���B�������ꂪ������Ă���Ƃ��Ȃ�3%�ȏ�̗�����B���ł���N���������܂����A����͉i...
���������̓n�C���X�N�V��̓��W�L���ȂǂŁA���ɐ����~�ł�3%�̗����𑱂���30�N�ςݏグ�Ă����A�V��̎����������ł��܂��Ƃ����L�����������܂��B�������A����Ȃ��Ƃ͐�ɋN���肦�Ȃ��̂ŐM���Ă͂����܂���B�������ꂪ������Ă���Ƃ��Ȃ�3%�ȏ�̗�����B���ł���N���������܂����A����͉i...
�����ł͑��肪��ł�
 ���������ň�ԑ�Ȃ��Ɗ���������FX������3�N�ȓ���9���̐l���ޏꂷ��ƌ����Ă��܂��B���ꂾ�����v���o��������͓̂�����ƂȂ̂ł��B���v�����ł͂Ȃ��A�����̏ꍇ�\������ɑΉ��ł����ɋ����I�ɑޏꂳ������Ƃ����P�[�X����ԑ������Ƃł��傤�B�Ȃ����S�҂͗��v���o�������邱�Ƃ�����̂ł��傤���B...
���������ň�ԑ�Ȃ��Ɗ���������FX������3�N�ȓ���9���̐l���ޏꂷ��ƌ����Ă��܂��B���ꂾ�����v���o��������͓̂�����ƂȂ̂ł��B���v�����ł͂Ȃ��A�����̏ꍇ�\������ɑΉ��ł����ɋ����I�ɑޏꂳ������Ƃ����P�[�X����ԑ������Ƃł��傤�B�Ȃ����S�҂͗��v���o�������邱�Ƃ�����̂ł��傤���B...
�����Ƀ`�������W
 �o�ς̕������˂�20��A30��̂��ЂƂ肳�܂͌o�ς̕������˂ē����Ƀ`�������W���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B���̎������Ė����͂����]�T�����ōs�����Ƃ���ł��B���������ł�FX�����ł����ۂɂ���Ă݂�ƌo�ς̓������ƂĂ��C�ɂȂ��Ă��܂��B�@�B���v���X�ɓ]�����Ƃ��ۗL������MSCI�ɑg�ݓ����ꂽ��...
�o�ς̕������˂�20��A30��̂��ЂƂ肳�܂͌o�ς̕������˂ē����Ƀ`�������W���Ă݂�Ƃ悢�ł��傤�B���̎������Ė����͂����]�T�����ōs�����Ƃ���ł��B���������ł�FX�����ł����ۂɂ���Ă݂�ƌo�ς̓������ƂĂ��C�ɂȂ��Ă��܂��B�@�B���v���X�ɓ]�����Ƃ��ۗL������MSCI�ɑg�ݓ����ꂽ��...
���������̋ɈӁi�O�ҁj
 ���ŗ��v���o�����߂Ɋ��������ŗ��v���o�������邱�Ƃ��ł���͈̂ꕔ�̌���ꂽ�����Ƃ����ł��B�قƂ�ǂ̓����Ƃ�3�N�ȓ��Ɋ����s�ꂩ��ޏꂷ��ƌ����Ă��܂��B���͊m���Ō���Ώオ�邩�����邩��50%�̂͂��Ȃ̂ɁA�ǂ����ĂقƂ�ǂ̐l�͕����Ă��܂��̂ł��傤���B�����͂��Ȃ���������A����̊���������...
���ŗ��v���o�����߂Ɋ��������ŗ��v���o�������邱�Ƃ��ł���͈̂ꕔ�̌���ꂽ�����Ƃ����ł��B�قƂ�ǂ̓����Ƃ�3�N�ȓ��Ɋ����s�ꂩ��ޏꂷ��ƌ����Ă��܂��B���͊m���Ō���Ώオ�邩�����邩��50%�̂͂��Ȃ̂ɁA�ǂ����ĂقƂ�ǂ̐l�͕����Ă��܂��̂ł��傤���B�����͂��Ȃ���������A����̊���������...
���������̋ɈӁi��ҁj
 �������܂߂ăg�[�^���ōl���銔�������̋ɈӁi�O�ҁj�ł́A�@�B�I�ɑ�����s�����Ƃ̏d�v���Ƌt�������̊댯���ɂ��Ă��b���܂����B�ł͎��ۂɊ��������ŗ��v���o��������ɂ͂ǂ�������悢�̂ł��傤���B���ŗ��v�邽�߂ɂ͋ɗ͕����Ȃ��悤�ɂ��ď��������Ȃ�������Ȃ��B�����̓����Ƃ͂��̂悤�ɍl���܂�...
�������܂߂ăg�[�^���ōl���銔�������̋ɈӁi�O�ҁj�ł́A�@�B�I�ɑ�����s�����Ƃ̏d�v���Ƌt�������̊댯���ɂ��Ă��b���܂����B�ł͎��ۂɊ��������ŗ��v���o��������ɂ͂ǂ�������悢�̂ł��傤���B���ŗ��v�邽�߂ɂ͋ɗ͕����Ȃ��悤�ɂ��ď��������Ȃ�������Ȃ��B�����̓����Ƃ͂��̂悤�ɍl���܂�...